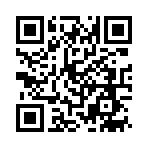2014年08月29日
《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 設立から介護経営サポートまで!
《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務
認知症・障害者の方が相続人の場合
◆相続人に認知症や障害者の方がいる場合
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。これは相続人の中に認知症の方や
障害者の方がいる場合でも同様です。ただし、その方が意思能力(正しい判断能力)を
有していないときは、遺産分割協議は有効に成立しません。このような場合、
家庭裁判所に「後見開始の審判」の手続きをとり、成年後見人を選任することとなります。
成年後見人は意思能力を欠いた相続人の代理人となり、分割協議に出席し、
必要な署名等を行うことになります(一般に、後見人は、その相続人の不利益にならないように、
法定相続分程度の遺産を取得できるよう協議を進めるようです)。
◆所得税・相続税の障害者控除の適用
成年後見制度における成年被後見人(家庭裁判所において「精神上の障害により
事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者)については、
H24.8の名古屋国税局文書照会で所得税法上、障害者控除の適用となる「特別障害者」に
該当することとされています。また、相続税法上の障害者控除の適用となる「特別障害者」
については、所得税法上の障害者控除の対象となる「特別障害者」に該当する者と規定しているため、
介護認定が低く、障害者手帳の交付を受けていない方でも、「特別障害者」として
所得税・相続税の障害者控除の適用を受けることができます
(H26.3東京国税局、文書回答事例)。
◆「納税管理人の届出」を後見人宛てに
成年後見制度は「自己の財産の管理・処分」を「することができない(後見相当)」
「常に援助が必要である(保佐相当)」「援助が必要である(補助相当)」という
判断能力の程度により3種類に分かれています。財産管理委任契約(見守り契約)を締結する場合には、
「納税管理人の届出書」を納税地(本人)の所轄税務署に提出し、申告書等の送付先・連絡先を
成年後見人宛にすることで、税金関係も後見人に対応してもらうことができます。
また、成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役になることができません。
取締役の方に成年後見人が付いた場合には、直ちに役員変更を行わなければなりません。
ツイート
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 設立から介護経営サポートまで!
運営:
福永会計事務所
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
06-6390-2031

2014年08月28日
《コラム》社会保険診療報酬と消費税転嫁

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 設立から介護経営サポートまで!
《コラム》社会保険診療報酬と消費税転嫁
H24.11.27 神戸地裁判決
◆社会保険診療報酬と消費税の転嫁の問題
平成24年11月、兵庫県の4つの医療法人が、現行消費税法の仕入税額控除制度は憲法違反であるとして、
国家賠償を求めていた裁判の判決が神戸地裁で出ています。医療機関の収入である社会保険診療報酬は、
社会政策的な配慮から消費税は非課税とされています。一方で、非課税売上のために行った仕入に係る消費税額は、
消費税の計算上控除することは認められていません。この控除できない仕入税額は、当然コストとなるため、
一般企業では、売価に転嫁することで回収を図ることになります。
◆医療機関は「転嫁をしたくてもできない」
医療機関の場合、社会保険診療報酬は公定価格であるため、この転嫁を自由に行うことはできません。
医療機関では、多額の控除対象外消費税が生ずるケースがよく見受けられますが、これは、
消費税の仕組み自体が法の下の平等・財産権の侵害など憲法に違反しているのではないかというのが
医療法人側の主張でした。消費税の非課税制度・仕入税額控除と診療報酬制度は、個々の制度としては
合理的であったとしても、これらが組み合わさった結果、医療機関には、一般企業に比べて、不公平な
「負担」が生じているということなのです。
◆地裁「法的負担でない」「報酬改定で考慮済」
この主張に対する裁判所の判断はNOでした。理由を噛み砕いて言えば、①消費税の仕入税額控除制度は、
「税負担の累積防止」という計算技術的なものであり、消費税法では、仕入税額を「事業者の法的負担」とは
位置付けていない、②医療法人と一般企業では、確かに「転嫁方法の区別」が生じているが、
診療報酬改定により一定の考慮がなされているため、立法裁量として許容できる範囲であるということでした。
◆EUでは課税選択制度(オプション)がある
EUでは上記のような議論を、医業特有の問題とは捉えていません。EUの付加価値税では
「仕入税額控除権」という請求権があり、課税適状となった時点で行使することができます。
非課税売上に対応する仕入税額が控除できず、事業者が不利益を被る場合には、
その売上を非課税とする取扱いを放棄して、課税取引を選択することで、仕入税額控除権の
行使ができる制度(課税選択制度)が設けられています。
ツイート
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 設立から介護経営サポートまで!
運営:
福永会計事務所
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
06-6390-2031

2014年08月27日
《コラム》離婚後の子をめぐるトラブル

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 設立から介護経営サポートまで!
《コラム》離婚後の子をめぐるトラブル
養育費負担がある場合の扶養控除
◆生計一親族の判定(養育費の負担)
国税庁ホームページの質疑応答事例には、子がある夫妻が離婚した後の「扶養控除(所得税)」を、
生活が別となった元夫・元妻のどちらに適用できるかという事例が紹介されています。元妻が子を引き取り、
元夫が養育費を負担しているケースでは、その養育費の支払いが①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」
など一定の年齢に限って行われるものであるときは、その養育費を負担した期間については、
子は元夫の「生計を一にしているもの」として、元夫は扶養控除の対象とすることができます。
ただし、養育費と慰謝料・財産分与の金額が明らかに区分できない場合には、この例には当てはまりません。
また、子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに、元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、
扶養控除はいずれか一方のみに適用されることになります。
◆「扶養控除」の取り合いになった事例
このようなケースでは、別れた元夫婦が子をどちらの控除対象扶養親族とするかという話し合いを持たずに、
両者が各々の控除扶養親族として申告を行ってしまうこともあるようです。争いになった事例として、
平成19年の国税不服審判所の裁決例があります。別れた元夫婦が各自の勤務先に扶養控除等申告書を提出し、
長女を各々の控除扶養親族として平成18年分の年末調整を受けていたというものです。このケースでは元妻が
扶養控除等申告書を職場に平成17年12月に提出し、元夫が平成18年1月に提出していることから、長女は、
先に扶養控除等申告書を提出した元妻の控除対象扶養親族と判断されました。
◆「決められない場合」の判定方法は2つ
所得税法施行令には、2以上の居住者が同一人を自己の扶養親族として申告書等に記載した場合の規定があります。
① 既に片方の居住者が申告書等の記載により扶養親族としている場合→その居住者の扶養親族
② ①によっても、いずれの扶養親族とするか定められない場合→合計所得金額の大きい方の居住者の扶養親族
上記の裁決では、①の段階で判定ができたため、元夫の所得の方が大きいという事実は考慮されませんでした。
ツイート
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 設立から介護経営サポートまで!
運営:
福永会計事務所
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
06-6390-2031

2014年08月26日
《コラム》専業主婦は年金未納に気をつけて

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 設立から介護経営サポートまで!
《コラム》専業主婦は年金未納に気をつけて
◆国民年金第3号被保険者が資格喪失する時
会社員や公務員の夫に扶養される専業主婦は年金の保険料はかかりませんが
受給資格が取れる国民年金の第3号被保険者となっています。しかしパート収入の増加や
夫が退職して自営業になった時等、3号の資格を失う時があります。
このような時は1号被保険者に変更手続きをして自ら保険料を納めておかないと
未納扱いになってしまいます。扶養の範囲とされる年収が130万円未満の範囲であっても
健保組合によっては月収で判断するところもあります。130万は前年の収入か、
これから先の見込額かの取り扱いも組合によってまちまちです。規約を確認してみましょう。
◆手続き漏れになりやすいケース
第3号被保険者に取得時の手続きは複写式の用紙で健康保険の被扶養者として
夫の勤め先で3号の届出も済んでいます。しかし資格喪失時は自ら変更の届出をしておく必要があるので
漏れが生じやすいのです。夫が退職して自営業になったり、定年退職した時に漏れが多いので注意が必要です。
夫が定年退職し再雇用になった時はどうでしょうか? 60歳定年退職し、年金受給できる年齢となった時に
年金減額を避けるため短時間勤務者となり、厚生年金に加入しない場合や、正社員と同じ勤務時間であっても
65歳になった時等いずれも60歳未満の妻は手続きをして第1号被保険者となり、保険料を納める必要があります。
◆資格期間の回復
日本年金機構の推計では第3号被保険者の資格を失ったのに、届け出ずに未納期間が生じてしまい、
そのままになっている人は47万人位いるといいます。 昨年7月から該当者の救済が始まっており、
順次通知が届けられています。手続きは「特定期間該当者届」を出しておけば、未納期間は年金額には反映しないが
受給資格期間(原則25年必要)に算入されます。 また、救済策として2015年4月から3年間に限り
過去最大10年分のうち希望する期間分を追納できます。未納で減ることになるはずだった年金額を増やし、
回復する機会となりますが、追納は強制ではありません。他の資産も考えた上で行いましょう。
ツイート
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 設立から介護経営サポートまで!
運営:
福永会計事務所
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
06-6390-2031